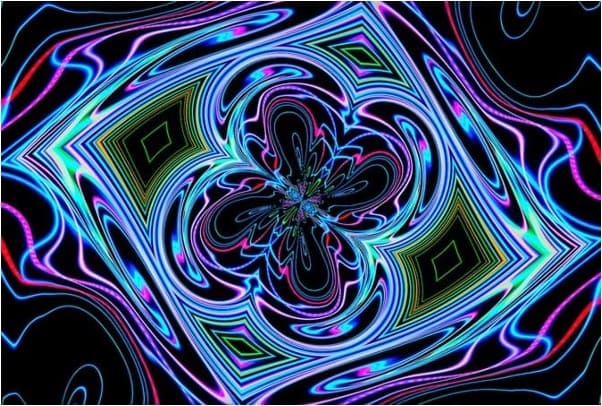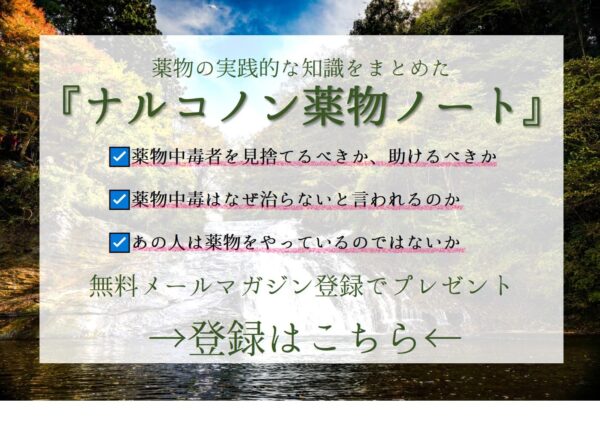クラブやレイブなど音楽のかかる場所で薬物が摂取されるのはなぜでしょう?音楽と薬物がセットになっているという認識は、少なからず私たちの中にあります。薬物で捕まったり、亡くなったりするミュージシャンが多いこと。今回はサイケ文化というものを中心に、薬物とクラブの結びつきについて考えていきます。
サイケとは
サイケデリック(psychedelic)とは、LSDなどの幻覚作用を持つ薬物の摂取によって生じる独特な感覚体験を指す言葉です。視覚や聴覚において、鮮やかな色彩、渦を巻くような模様、幻想的なイメージなどが特徴的に現れる状態を形容する際に用いられます。これらの視覚的特徴は、ペイズリー柄や幾何学的なパターンとして描写されることが多く、「サイケ」という略称でも親しまれています。
この語は、1950年代に精神科医ハンフリー・オズモンドが造語したものとされており、その語源には諸説あります。一つは「心理(psyche)」と「明らかにする(delos)」というギリシャ語を組み合わせたもので、「心の奥底を顕在化させる」といった意味が込められているとされています。オズモンドは1957年にこの用語を専門学会で紹介しました。

サイケデリックといえば、「ヒッピー」を中心に巻き起こったカウンターカルチャーに触れないわけにはいきません。「ヒッピー」とは、1960年代後半のアメリカに登場した若者たちの集団で、保守的な伝統文化からの解放を謳い、自由な生活を送っていた人々です。彼らの自由な思想、反体制的な信念は、奇抜な見た目に色濃く表れており、見る人に強い印象を与えます。そして彼らのライフスタイルはサイケデリックドラッグとは切っても切れない関係にありました。こうした影響を受けた日本の若者は「フーテン族」として新宿を中心に文化を形成していきました。
薬物とクラブの関係は?
サイケデリックカルチャーに詳しいライターの持田保氏によると、1980年代以降、欧米でテクノをはじめとする電子音楽をバックに、クラブや野外会場で踊るムーブメントが巻き起こったそうです。同時に流行したのがMDMAで、それをきっかけに各種ドラッグに手を出す若者が後を絶たなかったそう。LSDもサイケや電子音楽のシーンで好んで摂取されるドラッグの一つでした。
音楽にもサイケデリック〇〇というジャンルがあります。サイケデリックロック、サイケデリックポップやヒップホップなど。レイブ・サブカルチャーと結びついたアシットハウスやトランスといったジャンルもあります。こうした音楽を作り出す人は少なからず、LSD的な幻覚的作用なり世界観を曲に反映させようとしているんだと思います。

さて、クラブやレイブで薬物が蔓延するのは、音楽と一緒にキマりたいと思うからでしょう。薬物を摂取すると音の聴こえ方は変わります。なぜなら薬物は通常の知覚を大きく歪めてしまうためです。それらが神秘体験や非現実的な体験と誤認されて、薬物は乱用されます。もちろん、薬物を使わずに純粋な気持ちでそうした音楽を楽しむ人がいることも忘れてはいけませんが。
薬物を使用した末路
サイケデリックに限らず、薬物を摂取した人の末路は良いものではありません。後遺症に悩まされたり、薬物絡みの事故に巻き込まれたり。自分が空を飛べると思ってマンションから飛び降りたりなんかしたり。薬物に依存してしまうと、普通の生活に戻るのは簡単ではありません。

ここ千葉県市原市にある薬物リハビリ施設ナルコノンジャパンは、これまでに多くの薬物依存者を立ち直らすことに成功しています。適切なサポートを受けながら自分の努力で薬物をキッパリとやめる。簡単ではありませんが、ここナルコノンではそれが可能です。
薬物問題を抱えている方はご連絡ください。新しい扉を開くときです!
薬物やアルコール依存について情報を得たい方へ
薬物やアルコール依存の問題に関する情報を配信します。